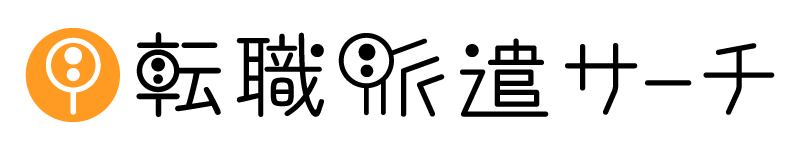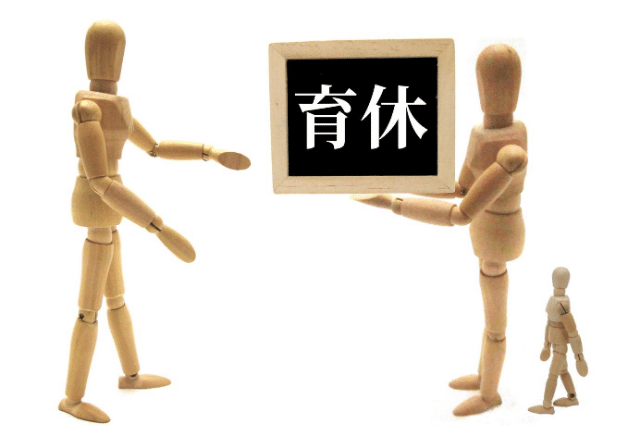目次
2025年7月 | 派遣会社 厳選3社


サクッと読める!ポイントまとめ
◆育休をとった女性の中には「保活の失敗」「心境の変化」などの理由で、復職を考え直す人もいる
◆育休明けの女性の中にも「産前と同じように働けない」ことがジレンマとなりキャリアチェンジを考える人もいる
◆産後もそれまでのキャリアを大切にしつつ無理なく働きたいのなら、派遣社員がおすすめ
◆育休取得後の退職に法的な問題はないが、マナーやけじめは考えるべき
働く女性の産休・育休と産後の働き方
仕事をしている女性が妊娠をした場合、産後も働き続けることを希望して、産休・育休を取得することはよくあります。
一定の期間は育児に専念し、子どもを保育園などに預けられるようになったら復職するという決めごとを、職場との間で行うわけです。
しかし、実際には育休を延長したり、場合によってはそのまま退職するという例も見受けられます。
ここにはどのような事情があるのか、また、やむを得ず退職することになった女性がその後も何らかの形で働き続けたいと思う場合、どのような方法があるのかについて解説していきます。
産休・育休とはどのような制度か
そもそも「産休・育休」とひとまとめに呼ばれがちですが、正確には「産前産後休業」と「育児休業」という2つの制度であることをご存じでしょうか。
「産休」は、出産の準備と産後の体の回復期間として、労働基準法により、出産するすべての女性に取得が認められている制度です。
一方「育休」は、子どもが1歳になるまでの間、希望する期間内で取得することのできる休業制度のことを指し、育児介護休業法で規定されています。
一定の条件を満たしていれば、正社員のみでなく、派遣社員やパート・アルバイトといった雇用形態の人でも取得が可能です。
また、育休は男性でも取ることができますが、この記事では女性のケースに焦点を当てて解説していきます。
産休と育休のうち、働く女性の復職に深く関わってくるのが「育休」です。
育休の期間中には「育児給付金」として
・産後6ヶ月以降…育休前の日給×育休の日数×50%
が支払われます。
そして育休の期間は子どもが1歳の誕生日を迎える前日までと定められているため、多くの母親はそれに間に合うように子どもの保育園入園を目指すことになります。
しかし、待機児童問題の深刻な現代、子どもを預けられる保育園が見つからないということも珍しくありません。
このような状況を受け、平成29年の法改正によって「保育園の申し込みをしているが入園のめどが立たない」などの条件を満たす場合、育児休暇の期間は最大2年まで延長されることになりました。
また、企業によっては独自の育児支援制度を整え、2年以上の育休が取得できるという例もあります。
育休中に復職を考え直す理由
出産後も働き続けることを希望して育休を取得したものの、育休の期間中に、復職を考え直したいと思うようになる女性も少なからずいます。
その主な理由としては、次の2つが挙げられます。
保活がうまくいかなかった
育休後に復職するためには、子どもを預ける保育園を決める、いわゆる「保活」が必須となりますが、前述のように保育園入園をめぐる状況は厳しく、預け先が見つからないという事態が起こっています。
入園申し込みをしていることを前提に育休の延長はできますが、一般的に、年度途中で空きが出ることは決して多くありません。
また翌年の入園を目指しても、子どもの年齢が上がるほどに定員枠が少なくなる保育園がほとんどなので、状況が大きく改善することはないようです。
このように具体的な復職のメドが立たないとなると、転職や退職など、自らの働き方を考え直す他ないということになります。
心境の変化
出産後の生活は、それまでと何から何まで一変します。
子どもが生まれると母親は24時間赤ちゃんのお世話に追われ、ひたすら赤ちゃんのことを考える日々です。
そのような生活の中「早く仕事に復帰したい」と思う人がいる一方で、「以前のように働く自信がなくなってきた」「久しぶりに職場に戻っても浦島太郎状態では」と感じる人がいるのも、無理のないことでしょう。
また、近いうちに次の子どもを望んでいる場合「復職してもまたすぐに産休・育休をとることになってしまう」ということに後ろめたさを感じる人もいます。
復職後に転職・退職を考える女性もいる
育休期間が終了して職場に復帰する際にも、働く女性を支援する仕組みはいろいろと存在しています。
労働基準法では、1歳未満の子どもを育てる女性は1日に最低30分×2回の「育児時間」を請求することが認められていますし、育児・介護休業法では企業に対し、3歳未満の子どもを育てる労働者には時短勤務制度を設けることを義務付けています。
他にも、多くの企業では復職前に上司などとの面談の場を設け、無理なく仕事に復帰できるようにサポートが行われています。
しかし復職する女性の側としては、「無理なく働きたいけれど、出産前と同様に活躍もしたい」という気持ちのジレンマに陥ってしまうこともあります。
特に、キャリアアップを重視して働いてきた女性の場合、一刻も早く出産前のようにバリバリ働きたいと思うこともあるでしょう。
周りがフルタイムで働く中、自分だけが時短勤務などを行うことで、迷惑をかけていると引け目に感じたり、置いていかれるようなもどかしさを感じてしまうかもしれません。
こういったことから、自分の働き方を考え直し始める人も見受けられます。
産後の働き方に派遣という選択肢
育休中や復職後、現在の働き方に限界を感じてしまったとしても「仕事自体は何らかの形で続けたい」と思う人も多いでしょう。
そのような場合の選択肢の1つとして、派遣社員で働くという方法が考えられます。
派遣という働き方にメリットは色々とありますが、特に正社員だった人が産後に派遣に転換する場合には以下のような点が魅力となります。
キャリアやスキルを活かした仕事が見つかりやすい
元々の職種が何であれ、産後に働き方の転換を考える人にとって、やはり「それまでのキャリアがもったいない」というのが本音ではないでしょうか。
とはいえ、退職や転職を考えている時点で、このままキャリアアップを第一に考えていくのには無理があると感じているはずです。
まず派遣社員という働き方は、雇用主が就業先企業ではなく派遣会社となり、お給料は時給で支払われるのが特徴です。
そして仕事に関しては、派遣会社が仲介役となり、本人のスキルや要望と企業のニーズをマッチングしてくれます。
自分のスキルをきちんと活かせる職場が見つかれば、働き方は変わってもそれまでのキャリアを捨てることにはなりません。
かつ、「職場内での競争」という意識から一歩下がることができるようになるのは、派遣の大きなメリットであると言えるでしょう。
週3日程度や時短での勤務ができる
派遣の仕事にはフルタイムばかりでなく、週3~4日程度や時短勤務の案件も多くあり、家庭と無理なく両立することが叶いやすくなります。
ここでポイントとなるのが、正社員として育休明けに認められる時短勤務との違いです。
正社員であれば、時短での勤務となると、それまでの業務を全てそのまま行うことは現実的に難しいでしょう。
「自分の担当分を縮小せざるを得ない」ということは、気持ちの上でしこりとなりがちです。
その点、派遣での時短勤務は就業当初から時短であることを前提に業務が組まれているため、ある意味で気の楽な、割り切った働き方が可能となります。
育休取得後の退職に問題はない?
育休というのは、いずれ復職することを大前提とした制度です。
育休中に給付金を受け取ることができるのも、あくまで「一定期間のみ働けない」という状況をサポートするためです。
では、その育休を取得した後に退職や転職をしても良いのでしょうか。
結論から言うと、法的には問題ありません。
最初から退職するつもりだったとすれば給付金の不正受給になりかねませんが、そうでなければ、出産という大きなライフイベントを経て環境や気持ちが変化するのは、致し方のないことと考えられます。
とはいえ、職場からすれば予定外に労働者を1人失うことになるので、他の従業員に負担をかけることになるのは事実です。
もしも育休を取得した後に退職をするのならば、この点を踏まえて円満退社を目指しましょう。
育休後、できる限り一旦は復職し上司に正直に事情を話したうえで、引き継ぎ期間をとって退職という流れが一般的です。
産後も無理なく働き続けたいのなら派遣がおすすめ
厚生労働省の調査によると、2018年度の女性の育児休業取得率は82.2%となり、多くの女性が産後も仕事を続けることに意欲的であることがわかります。
一方で、同年度の育休終了後の退職者率は10.5%となり「予定通りにはいかなかった」というケースも、やはり少なくはないようです。
女性が働き続けたいと思うのには、経済的な問題や仕事を通しての自己実現など人それぞれの理由がありますが、家庭との両立を考える場合、派遣社員はメリットの多い働き方です。
派遣会社では登録の際に面談があり、働き方の希望などを相談することができるので、現在育休中の人もまだその予定はない人も、先々の働き方に迷っていたらぜひ登録することをおすすめします。